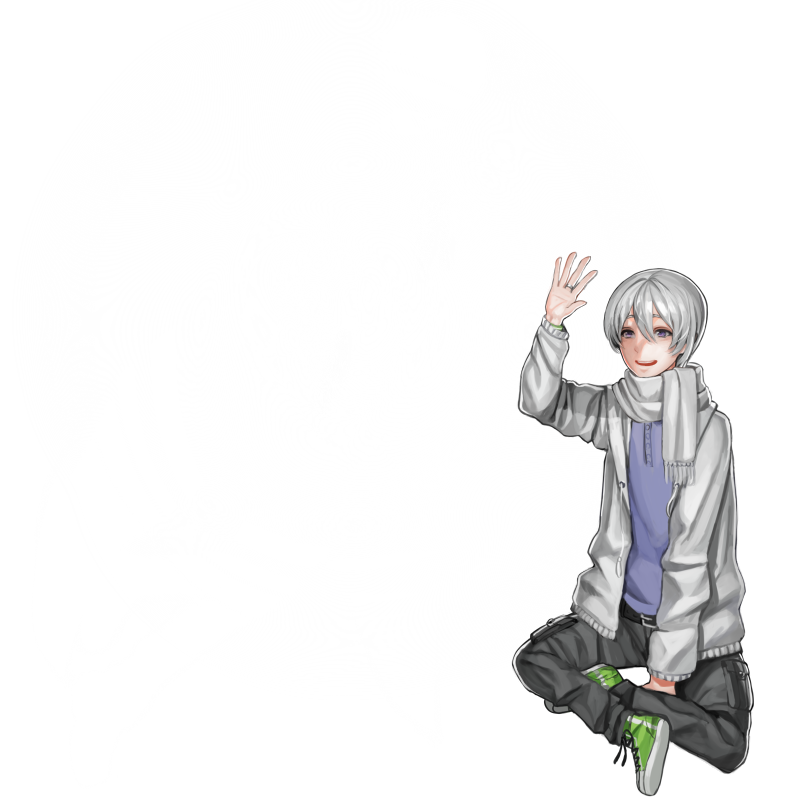いのるいしの、
-
#32016-09-09 / 21:34:24
『翳した右手』-2-
チャロアイト。
強い癒しの力を持つと言われるその石は、いつもフィリップを元気づけてくれた。
柔らかな手に包まれているかの様な、優しい感触が右手に伝わる。
その感触が心と体に溜まった毒気を、ゆっくりと溶かしていく。
溶けた心に浮かびあがるのは、亡くした両親との想い出。
意識しなければ薄れてしまいそうな記憶を、形見の指輪が繋げてくれる。
不意に陽光を、流れ雲が遮った。
ボロ切れの様な穴だらけの雲の隙間から射す陽光が、翳した手の向こうだけを照らす。
そこにきらめく靄が、掛かっていた。
影と光の狭間が現世との境を曖昧にしたのか、靄の中に人影が浮かぶ。
記憶の中で良く見知ったその影は、翳したフィリップの右手を両手で包みこんでいた。
愛犬が、吠える。
驚いたフィリップが瞬きするその間に、流れ雲と共に靄は去った。
相変わらず右手を包む、優しい感触だけを残して。
指輪にそっと左手を添えたフィリップの頬を、きらめく雫が、一筋伝った。
-
#22016-09-09 / 21:33:24
『翳した右手』-1-
凍てつく空気。
澄んだ空を見上げれば吐息が白く霞を掛け、その靄も一瞬で陽光を反射する結晶となり風に散る。
人も疎らな朝の住宅街を銀髪の少年、フィリップ・ヨソナラはポケットに手を突っ込み、愛犬と共に歩いていた。
通り掛かった公園の片隅で、陽だまりの中のベンチを見つけると、その上に胡坐をかく。
足も冷え切っていたのだ。
久しぶりの晴天に誘われ散歩に出たが、昼まで待つべきだったかもしれない。
長く垂らしたグレーのマフラーをもう一巻きすると、首を埋めた。
陽だまりは心地良く、凍てつく体を少しずつ温めていく。
リードをベンチの端に繋ぐと、愛犬も足元で丸くなった。
フィリップは思い出したように首元からペンダントを引っ張り出す。
現れたのは銀の鎖に繋がれた指輪。
陽光を受け白銀の輝きを放つ指輪を丁寧に外すと、右手の中指にはめる。
その手をかざすと自身の瞳と同じ色の、濃淡の紫が油彩画の様に混じり合う石を見つめた。
-
#12015-02-07 / 19:58:22
驚きの白さ、驚きの可愛さ!
お、何を見ているのかな?……指輪?大事なものなのかな?
それにしても、うーん……他にも何か見えるような……(目を凝らして)